
1966年から1976年にかけて中国全土を揺るがした「文化大革命」は、中国スポーツ界にも甚大な影響を及ぼした。これは単なるスポーツの衰退にとどまらず、スポーツのあり方そのものを根本から揺るがす大転換期となった。
■スポーツ体制の崩壊と混乱期(1966-1971年)
文化大革命が始まると、スポーツ界は激しい政治闘争の波に巻き込まれ、国家体育委員会をはじめとするスポーツ関連組織は急速に解体された。特に、北京体育大学の紅衛兵が国家体育委員会を攻撃したことを契機に、スポーツ指導者や選手たちは「ブルジョア思想の持ち主」「資本主義の手先」として糾弾された。1966年8月までに全国の地方体育委員会は機能停止に追い込まれ、さらに12月には『新体育』誌が廃刊され、公式スポーツイベントの開催が全面禁止された。
当時、国家代表選手の87%が農村へ強制移住させられた。世界記録保持者である重量挙げの陳鏡開や走高跳の鄭鳳栄でさえ「修正主義者」として糾弾され、競技の第一線から追放された。スポーツ専門学校1459校のうち93%が閉鎖され、競技人口は文革前の12%にまで激減した。
この期間、「大衆スポーツかエリートスポーツか」をめぐる論争が浮上し、エリートスポーツは「資本主義的堕落」とされ、人民日報はスポーツ施設を労働者・農民に開放するよう主張し、北京工人体育館が紡績工場の宿舎に転用されるなど、スポーツ施設の目的外利用が横行した。
■ピンポン外交と体制再編(1971-1976年)
こうした混乱の中、転機となったのは1971年の「ピンポン外交」だった。名古屋で開催された世界卓球選手権に5年ぶりに参加した中国は、アメリカ選手との交流を通じて外交的突破口を開いた。これは周恩来首相の指示によるもので、スポーツが再び外交戦略の手段として評価されるきっかけとなった。
これを機に、王猛将軍が新スポーツ相に任命され、組織再建が本格化した。五・七幹部学校から600人以上の幹部が復帰し、1972年までにスポーツ専門学校の72%が再開した。年間競技大会数は1974年には15,806回に達し、選手登録数も文革前の68%まで回復した。
この時期に導入された「三集中制度」(集中訓練・集中管理・集中学習)は、後の「挙国体制」の原型となり、特に卓球、体操、重量挙げの3種目で重点投資が行われ、練習時間は週50時間を超える厳しいものであった。
■スポーツ復興の政治力学
復興期においても、スポーツ界は激しい政治闘争の舞台であった。1972年から1976年にかけては、周恩来派と四人組の代理戦争の様相を呈し、鄧小平は「スポーツの軍事化管理」を提唱する一方、江青派は「農民スポーツ大会」を開催し、主導権を争った。1975年の北京国際マラソン大会の開催をめぐる3ヶ月間の論争がその象徴であった。
スポーツを通じたイデオロギー宣伝も復活し、1973年のアジア陸上競技選手権で金メダルを獲得した倪志欽は「毛主席の革命路線が生んだ英雄」として宣伝された。
■スポーツインフラの変容と国際再参入
文革期には都市部スポーツ施設の54%が地方へ移転され、北京工人体育館の卓球台が山西省の炭鉱町に移設されるなど、スポーツ資源の「階級的再配分」が行われた。
また、国際スポーツ秩序への再参入も進み、1973年の国際陸連復帰時には、アフリカ26カ国の支持を得て台湾を排除するなど、冷戦構造を利用した外交戦術が展開された。1974年テヘランアジア大会では第三世界との結束を強調するため、イランやパキスタンの選手との共同トレーニングも行われた。
■長期的影響と歴史的意義
文化大革命が中国スポーツ界に与えた混乱とその後の復興過程は、現代中国の競技システムやスポーツ政策に深刻な痕跡を残した。「挙国体制」は文革期に試行された集中管理システムを発展させたものであり、政治とスポーツの密接な結びつきは2008年北京オリンピックの開催理念にも引き継がれている。
この歴史的教訓は、スポーツが政治的ツールとしていかに国家統制や国際関係に影響を及ぼすかを考えるうえで、重要な視座を提供している。
【参考文献】
-
高津勝 (2009). 「文化大革命の中華人民共和国の学校体育・スポーツへの影響」. 慶應義塾大学体育研究所紀要, 48(1), 31-41.
-
李海鵬 (2020). 「文化大革命期の中国におけるサッカーと政治思想に関する研究」. 体育学研究, 33, 1-20.
-
徐本力 (2016). 『中国体育通史 第七卷:1966-1976』. 人民体育出版社.
-
伍紹祖 (2008). 『中華人民共和国体育史』. 中国書籍出版社.
-
熊曉正 (2014). 「”文革”時期的中國體育」. 體育文化導刊, 2014(5), 138-141.
-
劉波 (2018). 「文化大革命時期的中國體育:1966-1976」. 北京體育大學學報, 41(6), 7-14.
-
Fan Hong (1997). “Footbinding, Feminism and Freedom: The Liberation of Women’s Bodies in Modern China”. Frank Cass.
-
姚頌平 (2012). 『新中國體育60年』. 北京體育大學出版社.
-
董進霞 (2016). 「文化大革命時期的中國體育政策研究」. 體育學刊, 23(4), 1-6.
-
武浩文 (2013). 「中国におけるスポーツ政策の歴史的変遷に関する研究」. 博士論文, 筑波大学.

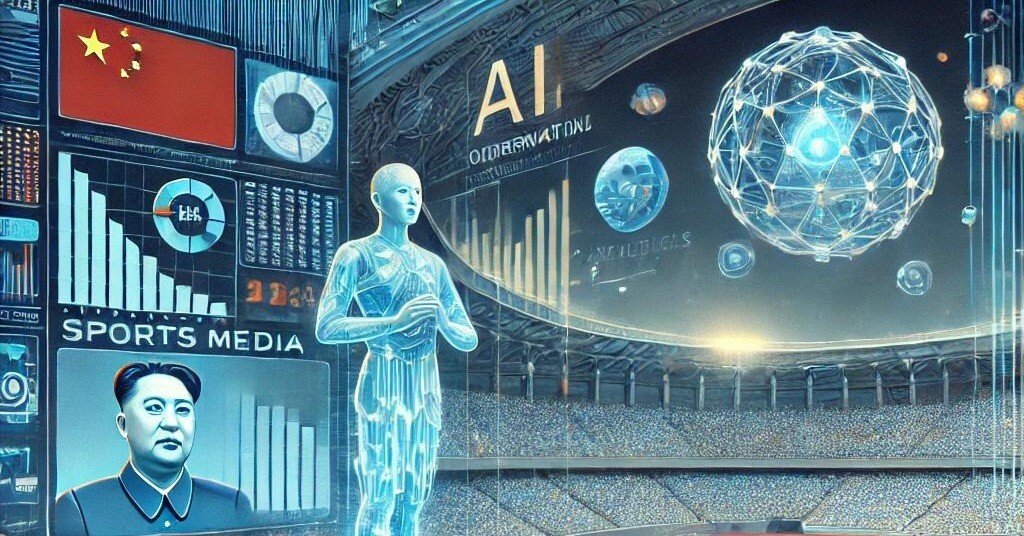

コメント